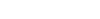ベイリー、ファーフッディ格言集④実験室と現場をつなぐもの
2015.09.03
チキンワークショップ2015
ボブ・ベイリー格言集④「実験室と現場をつなぐもの」
行動分析学は学問としての位置付けが明確でない。心理学の一部として発達したが、その基礎をつくったB. F. スキナー自身、自然科学の心理学とは分離されるべきだと言った。
データ(数字や記号)に基づいた物理や科学と違って、人間の心情に触れるところがあるため(だと思う)、行動の理論だけでは不十分、といった別要素をからんでしまうこともある。
ただ、その理由もわからなくない。行動分析学は大きく分けると、実験室の中でラットやハトを使った「基礎研究」を行う分野と、教育や医療の場での運用を進める応用研究のふたつ。このふたつの中間をつなぐものがほとんどないのだ。
それはある意味で動物なのだが、でもどんなに実験室のハトはこうすればこう行動をする、と示されても、現実社会でどれだけそれがクリーンに行えるのか?
先日、日本行動分析学会の総会に出席した。何かと極端なアメリカ人に比べて日本人はバランスが取れていると実感したのだが、この中でもひとつの大きなテーマが「基礎と応用」をつなぐことだった。
私にとってはこの溝を埋めるのが、ボブとパービーンのワークショップだ。
教科書の中で示される手法や方程式、褒美と罰…それが、実際に目の前で自由に振る舞う動物を相手にどう働くのかが学べる。個々の定義ではなく、実験用のプログラムではなく、自分の手を通して目の前で動いている動物との駆け引き?微調整?を繰り返しながら総合的にまとまっていく、という感じ。知っているかいないかで、体が動くか動かないかで、効率がまったく違う!
アメリカの行動分析分野についてボブが指摘していたのは、基礎研究が実験箱の中でハトの「つつく」行動の実験ばかりやりすぎだ、ということだったのだが、その意味を私なりに解釈すると…
犬というのは、実験室で生活しているのでも、動物園で生活しているのでもない。かといって人間ほど人権(犬権)が守られているのでもない、いわば中間の世界に住む生き物だ。その犬(や一部の動物)のトレーニングの世界では、当たり前のように考慮されること…例えば、褒美の種類によって得られる行動が違う、とか、犬の習性に根ざした行動かそれともより学習された行動なのかを考慮しないと、「褒美」を与えれば行動が改善するわけではない、といったようなことがある。でもそのようなデータは実験箱の中ではほとんど取られてきていない。(水と餌について研究を始めた先生がいました!)
ハトにとってもニワトリにとっても、「つつく」という行動は、「安い行動」(cheap behavior)なのです。そうではなく、よりエネルギー消費をともなわなければならない行動が対象になったとき、何が起こるか、そのときどうしたらいいのかを知る、それがより複雑な現実社会であり、それが絡み合うのが応用現場だ。
ボブは決して自分を行動分析学者とは呼んでいない。それよりも「生物学者」であり、動物トレーニングにおいては「技術屋」だと言っている。1960年代からの経験で、行動の法則を自由自在に扱うことを熟知しているのだ。
ボブはまた、昔から「パブロフはつねにあなたの肩に乗っている(Pavlov is always on your shoulder)」の表現で知られている。それは、どんなにオペラントな学習でも、必ずレスポンデント(古典的条件付け:感情面)の部分があり、決してこれを無視しては絶対に成功しない、といこと。
人間のトラウマ治療などの分野では、感情と記憶の役割について注目され研究が盛んになっている。残念ながら行動分析の分野ではなく、主に神経科学の分野だが、犬のトレーニングでも活用できる情報がたくさんあった。